オーストリア=ハンガリー帝国最後の皇帝カール1世の皇后ツィタ。
オーストリア共和国により夫が皇帝退位を追われ、家族で亡命。早逝した夫を見送った後も、スペイン、ベルギー、カナダなどを渡り歩きました。元皇帝カールの死から60年以上がたった1989年、ツィタは96歳で生涯を終えました。
19世紀世界が大きく動いていった時代、エネルギッシュな性格と曲りない意思で皇帝を支えたツィタ。帝国の崩壊を見届け激動の時代を生き抜いた女性。この記事では、ハプスブルク家最後の皇后の人生をみていきたいとおもいます。
- パルマ公の娘で、幼い時からハプスブルク家と交流があったツィタ
- 未来の皇帝カールの元へ嫁ぎ、夫をエネルギッシュな性格で支え続けた
- 夫が早逝した後も一家の中心となり、一家の権威を守り抜いた
未来のオーストリア皇后
1892年5月9日、イタリア王国のルッカ近郊ピアノーレ城で誕生したツィタ・フォン・ブルボン=パルマ。ブルボン=パルマ家のパルマ公の娘でありました。1903年9月16日から、ツィタはバイエルンのツァングベルクにある聖ヨゼフ修道院で、高貴な身分にふさわしい教育を受けました。
学業成績は優秀ではなかったものの、努力もあってドイツ語を習得しました。フランツ・ヨーゼフの招きで度々宮殿を訪れており、そこでは将来の夫となるカールとも交流がありました。また各国の亡命した君主たちとも関わりがあったそうで、それは彼女の性格を形成していく上で、重要な影響を与えたといいます。
カールとの再会
1909年初夏、ツィタはいとこマリアとともに訪れた、フランツェンバートにてカール大公と再会しました。カールは当時エーゲルラントの竜騎兵中隊に駐屯しており、そこから軍服で訪れていたそうです。当時の帝位継承者であった「フランツ・フェルディナント大公」は、身分違いの妃と結婚したため『子孫の皇位継承権は放棄すること』を皇帝に誓っていました。

また老帝フランツ・ヨーゼフ1世との政治思想的対立も深まっていました。
そこで次期帝位継承者として期待されいていたカール大公は、カトリックで身分も申し分ないツィタとの婚約を決めたのです。政治的な決定かと思いきや、ツィタは後年になって「私のカールに対する愛情は、2年間の間にゆっくり熟成されていきました」と語っています。
祝福された結婚
このような情勢下、愛情から、そして政治的判断からも交際を開始した二人。フランツ・ヨーゼフ1世がカールを呼び出し「そろそろ自分にあった結婚相手を見つけなさい」と説いたのが1910年秋のことでした。というのも、当時のハプスブルク家の結婚は容易ではなく、
- カトリック信者であり
- 現在または過去において、当地に当たった君主の子女
という厳しい条件がついていました。
1911年5月中旬カールは、すでにツィタと婚約していたわけですが、ヨーゼフ1世はそれを知らず。カールの母マリア・ヨーゼファにより、婚約の知らせを受け取ったヨーゼフ1世は大変驚いたそうです。デンマーク王女との結婚を考えていた皇帝でしたが、ツィタがパルマ公国の公女であり敬虔なカトリック信者でもあったので、老帝は納得してふたりの結婚を祝福しました。
 (カールとツィタの婚礼。前列右はフランツ・ヨーゼフ1世)
(カールとツィタの婚礼。前列右はフランツ・ヨーゼフ1世)
スポンサーリンク
オーストリア共和制の台頭
1916年11月、フランツ・ヨーゼフ皇帝が崩御して29歳で即位した後、もろくなった君主制の焦燥感に駆られ、カールは指導者としての自覚を欠いていた、ともいわれています。
彼は近代的な君主として、
- 仰々しい宮廷儀式を廃止し、
- 電話などの現代機器を取り入れたり、
- 勤務形態や社交形式などを改めさせたり、
人民の皇帝として、頭角を現しましたが、ときに急な方向転換が物議を醸すこともありました。
皇后となったツィタはエネルギッシュな性格と曲がりのない意志で、動揺している夫を決断に駆り立てました。皇后として彼女は政治的に重要な位置にあり、どこへいっても政治的に劣った夫に付き添ったそうです。
皇帝の地位をおわれて、スイスへ亡命
まもなくドイツ皇帝ヴィルヘレム2世が退位宣言をし、ドイツでは社会民主党の主導する政権が誕生しました。それをうけてオーストリア社会民主党も、皇帝に退位するよう要求しました。カール1世は抵抗しましたが、『国事不関与 (政治には一切関与しない)』という書面にほぼムリやりサインをさせられ、なんとか『皇帝』の地位は保ったけれどもはや形だけ。
2月には宮殿の周辺を200人もの赤軍が囲っており、一家の命が危ないとして、カールはスイスへの亡命を真剣に考え始めました。「近々オーストリア皇帝一家が虐殺される」との情報を受け、助けに出たのはイギリス政府でありました。

縁戚であったロマノフ家が一家惨殺されたことをうけ、見殺しにしたと非難をうけていたイギリスは、ハプスブルク家の出国には協力せざるをえないという事情もあり、見事な交渉の末カール一家は、『皇帝』のままお召し列車でスイスへの亡命を果たすことに成功したのです。
ハプスブルク帝国の崩壊
3月23日皇帝一家は、オーストリアを出国しました。
そしてレンナーが国民議会に提出した、「ハプスブルク家は永久に統治権および、すべての特権を失効する」という法案が4月3日に可決されました。王冠に基づいた財産のみならず、ハプスブルク家の私的財産のほとんどが共和国に没収されました。
カールはロシア革命を警戒し『ドイツとの同盟の解消と独立平和条約の締結』を求め、1916年末、ツィタの兄弟であるブルボン=パルマのシクストゥスを仲介者としてフランスと秘密交渉を始めた….のですが、その内容が漏れてドイツは激怒。ドイツからは裏切り者として、帝国内でも皇帝に対しての疑惑がつのりカールへの信頼は失墜しました。
スポンサーリンク
皇帝カール1世の崩御
1918年、同盟国側の戦線崩壊とともに各民族が相次いで離反。
チェロスロバキア、ポーランドが共和国宣言をし、帝国は崩壊していきました。ボヘミア、クロアチア、グリティアなどで暴動が起きようとしていることも知り、11月3日カールは正式に帝国連邦化を宣言し無条件降伏をしました。
カール1世 (カーロイ4世) はハンガリーから2回クーデターを起こしましたが、政権奪回には失敗。時代の波にあらがわことはできず、最後のオーストリア皇帝は亡命先のスイスで亡くなります。享年34歳の若さでありました。
その後のツィタ
カールはツィタへ「これからはスペイン国王アルフォンソ13世を頼みとしなさい、彼は私の家族を助けてくれると約束した」といい、早すぎる彼の葬儀には、3万人が参列しました。そして、カールの死から60年がたった1989年3月14日、オーストリア元皇后ツィタは96歳で死去しました。
 (晩年 帝国時代の経験についてインタビューを受けるツィタ元皇后)
(晩年 帝国時代の経験についてインタビューを受けるツィタ元皇后)
1982年までオーストリアへの入国が許されなかったハプスブルク家一族ですが、ツィタの葬儀はウィーン宮廷の伝統的な様式にしたがって行われました。これはオーストリア共和国とハプスブルク=ロレーヌ家間の和解の象徴だともいわれました。
亡命中も、クーデターの際も夫を支え続けた皇后ツィタ。1922年、夫が亡くなったあとツィタは、ハプスブルク=ロレーヌ家の中心人物となりました。ハプスブルク家の継承者として、長男オットーを育て彼の政治的野心を積極的に支援しました。ツィタはまた『カールの列福』にも力を注ぎ、2004年にカールは福音となりました。(列福:キリスト教、カトリック教会において徳と聖性が認められ、聖人に次ぐ福者の地位に上げられることをいう)
スポンサーリンク
あとがきにかえて
ツィタはハプスブルク王位継承者として長男のオットーを育て、彼が過半数を獲得した後、彼の政治的野心を積極的に支援しました。その権威のおかげで王位を失った後の困難な時期にも、元皇后はハプスブルク=ロレーヌ家の中心人物でいることができました。
1960年代初期から、ツィタはスイスのジゼルにあるカトリックの老人ホームで隠棲生活を送っていたそうです。夫を早くに見取り、この激動の時代の変わり目を生き抜いた彼女。この大きな時代のうねりは、彼女の目にどう写っていたのでしょうか。
彼女の回顧録は歴史を語るにあたりとても重要な文献であり、ハプスブルク家の擁護者のなかではとくに大切に扱われているそうです。ハプスブルク家の現在については、こちらの記事 (【ハプスブルク家の末裔】巨大王朝 | 華麗なる一族の末路) にまとめております。
この記事を読んだ人へおすすめの記事


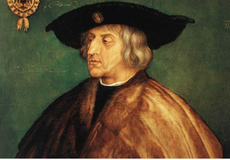
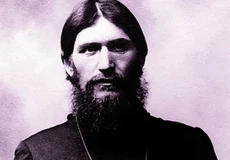




コメント